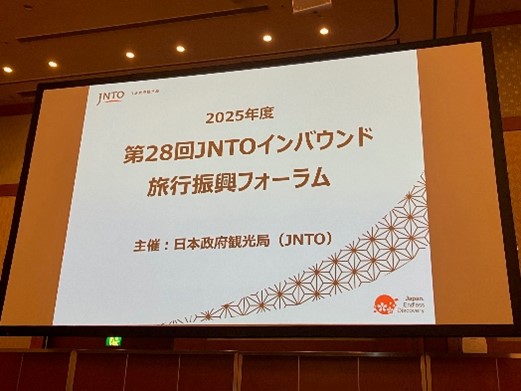本ページでは、2025年9月4~5日に開催されました
「第28回JNTOインバウンド旅行振興フォーラム」の
詳細レポートをお届けします。
プログラムは、最新の市場概況と訪日マーケティング戦略に基づいた取組事例の発表、
テーマ別では高付加価値旅行や、官民連携の取り組み事例などのトークセッションも行われました。
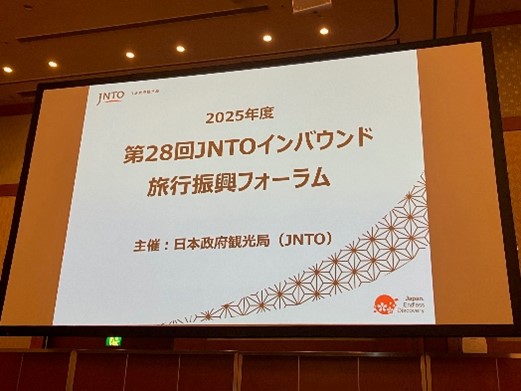
 「米州市場の最新動向」講演写真:(左)ニューヨーク事務所長 松本将/(左から2番目)ロサンゼルス事務所長 田中陽子/
「米州市場の最新動向」講演写真:(左)ニューヨーク事務所長 松本将/(左から2番目)ロサンゼルス事務所長 田中陽子/
(右から2番目)トロント事務所長 鈴木結佳/メキシコ事務所長 山田麻須美 *敬称略市場ごとの講演内容を振りかえるにあたり、
7つの観点をお伝えしていきます。
【1】市場別の旅行シーズンと「狙い目」のタイミング市場によって海外旅行の繁忙期が異なり、これを理解して地域の資源をマッチングさせることが、
より効果的な誘客に繋がると改めて感じました。
例えば、講演で紹介された
インド市場は、最大の旅行シーズンが4月~6月、特に5月がピークとのこと。
これはまさに、日本のゴールデンウィーク後の観光需要が落ち着く時期と重なり、
閑散期対策としてマッチングしやすいです。
同様に、
中東市場も自国の酷暑を避ける夏が旅行シーズンであり、
夏の山岳・高原リゾートのグリーンシーズン観光との組み合わせや、
豪州市場は南半球の夏休みである12月~2月に日本の
「雪」を求めて訪れるため、
日本の観光シーズンの平準化に貢献しやすいと感じました。
市場別に海外旅行の繁忙期が異なるため、
地域で受け入れたい季節とマッチしやすい市場はどこか、季節ならではのコンテンツとマッチしそうな市場はどこかを改めて検討してみるのはよいと思います。
また、
英国市場では、旅行会社が翌年の商品を造成・販売する繁忙期が1月~3月に集中するため、
この時期の商談や招請は避けるのがマナーというお話も。
プロモーション連携先のスケジュール感を把握することも重要です。
【2】市場に響くプロモーションの工夫各市場で利用されるメディアを理解し、上手に活用することの重要性も、多くの講演で語られていました。
例えば
訪日慣れした個人旅行者が急増中の中国市場では、
若者に人気のSNS
「RED(小紅書)」で、
『陶器×美食』といったテーマ性のある投稿や、
『混雑を避けられる紅葉スポット』といった実用的な切り口が大きな反響を呼んでいるそうです。
こうしたSNSでの工夫に加え、
フランス市場の事例も非常に示唆に富んでいました。
フランスで人気の旅行ガイドブックサイト「Routard」には、旅行者同士が情報交換する活発な掲示板があります。
そこで、
「日本へ行くことは決めたけれど、まだ詳しい日程は未定」という旅行者に対し、日本の観光のプロが旅の相談に乗る、というユニークな取り組みが行われました。
専門家が自然な形で地方の魅力を紹介することで、ゴールデンルートだけでなく、
様々な地域へ興味を持ってもらう効果的なアプローチだと感じました。
【3】競合としての「中国」の存在感今回、多くの市場で海外旅行先の候補として「中国」の名前が挙がっていたのが印象的でした。
特に
タイ市場では、相互査証免除や価格の安さを背景に、日本と並ぶ
「二大人気目的地」とまで言われています。
この事実は、私たちがつい日本国内の地域間競争に目を向けがちな中、
海外の旅行者は常に日本と他の国を天秤にかけているということを意識しなければと感じました。
アジアの中での日本、そして皆様の地域の差別化ポイントを明確にすることが、今後ますます重要になるでしょう。
また、ロングホール市場からの誘客を考える上では、
アジアのハブ空港の活用も重要な視点です。
例えば
英国市場では、訪日客の約半数が香港や韓国などを経由して日本を訪れているというデータが示されました。
これは、
アジアの主要空港が、日本の地方都市への新たな玄関口になる可能性を示唆しています。
アジアの近隣国と日本を組み合わせた広域ルートを提案することも、これからの新しい旅の形として注目できます。
【4】国際情勢と旅行者の心理と可能性国際的な政治状況が、旅行者の行き先選びに与える影響についてもリアルな話が聞けました。
例えば
カナダ市場では、アメリカへの好感度が低下し、旅行を控える動きがあるそうです。
これにより、
冬の長期滞在先を探す「スノーバード」層が
新たな旅行先を模索しているという話は、日本にとってのチャンスかもしれません。
一方で
アメリカ市場は、旅行需要自体が好調で影響は限定的とのこと。
このように、国際情勢の変化はリスクであると同時に、新たな需要を生む可能性があるため、
マクロな視点で旅行者の心理の変化を捉えることの重要性を感じました。
【5】地方誘客の鍵は「人とのふれあい」を伴う Authentic な体験最近のインバウンドのキーワードとして、
「体験重視」「少人数旅行(FIT)」「地方志向」が挙げられていました。
これは、単に有名な観光地を巡るだけでなく、「日本ならでは」の文化に触れたり、
まだ知られていない(”Off the beaten path”)場所を訪れたいという旅行者の強い意欲の表れです。
特にインバウンドニーズにマッチする事例として紹介された地方の体験コンテンツでは、
「地域の人とのふれあい」がありました。
例えば、長崎県島原市の「伝統野菜収穫体験」では、地元農家の方の無農薬栽培にかける情熱に触れ、
一緒に収穫するという体験が高く評価されています。
また、福井県の「越前和紙工房」では、職人とやりとりしながら紙漉きを体験することで、
その土地に受け継がれてきた和紙のストーリーに触れる”Authentic”な体験だと評価されています。
丹波篠山のサイクリングツアーでも、地元ガイドによる文化や歴史の説明が、
その土地を訪れる意味を深く理解させたと好評とのことで、単なるアクティビティの提供に留まらず、
そこに
住む人々の想いや暮らしに触れることが、旅行者の心に響く重要なポイントになっているようです。
また、米州市場では新しい旅行の形も生まれていると紹介されていました。
ガイドも参加者も女性で構成される
「女性限定ツアー」や、
一人で旅に出て現地で友人と合流して楽しむ
「Z世代のソロ旅行」が注目されています。
韓国市場では
「平成レトロ」が人気を博しており、市場ごとの細やかなトレンドを捉える必要がありそうです。
【6】最新トレンドとしてデジタル活用の更なる高まり情報発信の手法も日々進化しています。コロナ禍以降、
旅行の情報源として「SNS」の重要性が増しており、特に
「ショート動画」の活用が鍵となっています。
JNTOのInstagramアカウントの投稿の中から岡山県倉敷市の事例が紹介され、
冒頭にインパクトのあるカットを配置し、約1秒ごとにテンポよくシーンを切り替える動画が
高いエンゲージメントを獲得したと報告されていました。
さらに、AI市場の急成長も見逃せません。
旅行者がChatGPTなどの生成AIで情報検索や旅行計画を行うのが当たり前になりつつあり、
これからは生成AIに最適化されたコンテンツを作成する
「AIO対策」の重要性が増すという話もあがりました。
【7】「食の多様性」への対応が、新たな誘客の鍵に最後に、今回のフォーラムを通じて、改めて
「食」への対応の重要性を感じた点についてお伝えします。
特に
台湾市場では、人口に占めるベジタリアンの割合が世界第2位であり、
団体ツアー客の10%以上から食事対応の要望があるというデータが示されました。
現地の旅行会社からは「日本では特別食に対応できる施設が少なく手配が難しいが、
高級ツアーでは対応が必須」という切実な声も聞かれました。これは台湾に限りません。
インド市場では
ベジタリアン対応、
インドネシア市場や
マレーシア市場、
中東市場からの旅行者を迎える上では
ハラル対応やそれに関する詳細情報が求められます。
「食」は観光の満足度に直結する重要な要素です。
特別食への対応可否に関する情報を地域で整理し、積極的に発信していくことが、
これからのインバウンド誘客強化や満足度アップにつながるでしょう。
みなさま、いかがでしたでしょうか。少しでも気づきがありましたら幸いです!
じゃらんリサーチセンターでは、JNTO協力のもと、
毎年インバウンド注力ターゲット調査も行っております。
https://jrc.jalan.net/surveys/inbound_target/
JNTOインバウンド旅行振興フォーラムの取材記事を担当した
松本百加里の研究内容は下記より確認ください。
インバウンド都道府県ポジショニング調査2025
https://jrc.jalan.net/surveys/inbound-positioning/
インバウンド旅行者の主要周遊ルート調査2025
https://jrc.jalan.net/research/6259/
【とーりまかし記事】生成AIで回す!観光戦略の「新・循環」
https://jrc.jalan.net/research/6423/